駅伝の感動はその由来を知るともっと深まります!
年末年始にテレビをつけると、よく見られるスポーツが駅伝。
沿道の歓声、風を切って走る選手の姿、そして手に汗握る「襷(たすき)の受け渡し。
駅伝は日本中が熱狂するスポーツの代表です。
そして、駅伝はただの長距離走のリレーではありません。
今から約100年前に生まれた長い歴史があり、チームの思いや絆を繋ぐ精神性が深く関わる日本独自のスポーツであり、文化です。
- 「えきでん」という言葉の語源は?
- なぜ日本で独自の発展を遂げたのか?
- そして、襷の受け渡しはなぜ感動的なのか?
本記事では、駅伝ファンなら知っておきたい、「駅伝」という言葉の語源、日本で最初の駅伝。駅伝に欠かせない「襷(たすき)」の深い意味について解説します。
この記事を読み終えた後、あなたの駅伝観は大きく変わっているでしょう。
駅伝の由来とは?【言葉の起源】
私たちが何気なく使っている「駅伝」という言葉は、スポーツのために作られた造語ではありません。
駅伝は昔の日本の交通・通信制度だった
駅伝という言葉の語源は、古代から江戸時代にかけて、日本の重要な公的な交通・通信システムとして機能していた「駅馬・伝馬制(えきば・てんませい)」にあります。
駅(えき)は、中央から地方へ派遣された公務の使者が、馬を乗り継いだり宿泊したりするための施設。伝(でん)は、一般の使者が荷物や公文書を運ぶために人足(伝馬)や馬を乗り継いでいくシステムです。
つまり、駅伝とは公文書などを人や馬でリレーしながら運ぶ制度そのものを指していました。
駅伝でランナーが襷(メッセージ)をリレーで繋いでいく姿は、まさにこの古い交通制度を現代に再現していると言えるでしょう。
命名者は誰?最初のレースで生まれた名前
「駅伝競走」という名称が正式に決定したのは1917年(大正6年)。日本で最初の長距離リレー大会が開催された時です。
この記念すべき大会の企画・運営に携わったのが、詩人であり歌人でもある土岐善麿(ときぜんまろ)氏でした。
土岐は長距離をリレーで繋ぐという競技に日本の歴史と文化を感じさせる名前を付けたいと考え、前述の「駅馬・伝馬制」にちなんで「駅伝」という名を提案しました。この提案が採用され、「駅伝競走」として定着することになったのです。
「リレーマラソン」と欧米らしい名前にせず、あえて日本の歴史的な背景を持つ言葉を選んだことで、駅伝は日本文化と精神性を帯びた競技として進展していきます。
競技としての「駅伝」誕生秘話【競技の起源】
駅伝という言葉が誕生した背景が分かったところで、次は「競技」としての駅伝が、いつ、どこで始まったのかを見ていきましょう。
日本初の駅伝はいつ?「東海道駅伝競走」
日本初の駅伝競走は、1917年(大正6年)4月に開催された「東海道駅伝競走」。
この大会は、当時の大イベントであった「東京奠都(てんと)50周年記念」の一環として、読売新聞社によって企画されました。
コースは京都・三条大橋をスタートして東海道をひた走り、ゴールは東京・上野の不忍池(しのばずのいけ)。総距離約516km(32区間)もあり、3日間に及ぶ壮大なレースでした。
当時の人々の熱狂ぶりは凄まじく、初めて目にするこの壮大なリレーを一目見ようと、沿道には数多くの人々が詰めかけました。この東海道駅伝競走の成功が、駅伝が日本の国民的イベントへと発展する大きな一歩となりました。
なぜ日本で独自の発展を遂げたのか?
長距離のリレー競技は世界にもありますが、駅伝のように国民全体が熱狂し、文化として深く根付いている国は稀です。
なぜ駅伝は日本でこれほどまでに発展したのでしょうか?
①日本の集団主義的な文化との親和性
駅伝は個人競技であるマラソンとは異なり、複数の走者が一つの目標に向かって力を合わせるチーム競技です。
個々の走力はもちろん重要ですが、それ以上に「仲間を思い、襷を繋ぐ」という集団としての絆や努力が重視されます。
古来より稲作文化などを通じて育まれてきた日本の「チームワーク」や「協調性」を重んじる文化が駅伝と非常にマッチしていました。
② 新聞社によるイベント化とメディア戦略
駅伝は黎明期から読売新聞社や東京日日新聞社(現・毎日新聞社)などの主要な新聞社が、自社の事業として企画・主催してきました。
メディアが大々的に報道することで、駅伝はすぐに全国的な注目を集め、国民の熱狂的な支持を得るに至りました。
特に箱根駅伝は、各校の「絆」や「青春のドラマ」を交えて報道することで、多くの感動と共感を呼ぶ結果となり、国民的イベントとしての地位を確固たるものにしました。
「襷(たすき)」に込められた特別な意味【文化・精神的な起源】
駅伝を語る上で欠かせないのが「襷」。
世界のリレー競技で使われる「バトン」とは異なり、日本の駅伝の襷には文化的な重みと精神的な意味が込められています。
襷は「バトン」ではない
バトンがプラスチックや金属でできた道具であるのに対し、駅伝の襷は主に布製です。
この布製の襷には様々な思いが染み込んでいきます。
襷の原型は「公的な目印」
襷がなぜ布製なのか、その由来は諸説ありますが、前述の「駅伝制」にも関連付けられています。
駅伝制で使われた公文書を包んだ布や、身分を示す目印などが現代の襷のイメージに繋がっているという説があります。つまり、襷は「大切なものを運ぶ」「任務を負っていることを示す」という意味合いを持っているのです。
襷が持つ「生命」の意味
布製の襷は、前の走者が走る間に汗や体温で温められ、次の走者に渡されます。
襷は前の走者の「生命」や「思い」が乗り移ったものです。
そして、襷を受け取るということは、仲間が作り上げてきた努力、喜び、苦しみをすべて引き継ぎ、「次の区間を任された」という重責を背負うことを意味します。
駅伝における「襷を繋ぐ」という精神性
襷の継承は、最もドラマが生まれる瞬間です。
ランナーは襷を繋ぐために、ときに体調不良や怪我を抱えながらも、限界を超えて走り続けます。それは「チームの目標を達成するため」「仲間の思いを途切れさせてはならない」という、極めて強い責任感と献身の精神からくるものです。
もし襷が途切れてしまうと、それまでの区間を走った仲間の努力が無になってしまう。このプレッシャーと感動が他のスポーツにはない駅伝独自の深みを生み出しています。
襷を繋ぐことは、歴史を繋ぐこと、未来へ希望を繋ぐことであり、駅伝はまさに「日本人の絆の精神」を体現していると言えるでしょう。
まとめ 駅伝の由来を知ると、もっと感動できる!
私たちを熱狂させる駅伝のルーツについて、言葉の起源から競技の歴史、そして襷に込められた精神性について解説してきました。
- 言葉の由来:「駅馬・伝馬制」という日本の古い交通システムに由来し、詩人の土岐善麿氏らが命名
- 競技の起源:1917年(大正6年)の「東海道駅伝競走」が始まり。日本の集団的な文化とメディア戦略によって国民的スポーツへと発展
- 襷の意味:バトンではなく、走者の思いと命が詰まった、日本の精神性を象徴する特別な文化
駅伝はただ速さを競うスポーツではありません。
日本の歴史と文化の息が吹き込まれ、「一つになること」の美しさを教えてくれるスポーツです。
次に駅伝を観戦する際は、ぜひこの「由来」を思い出し、襷が持つ重みや、仲間を思う精神に注目してみてください。
きっと、今までとは違う感動と興奮を味わえるはずです。
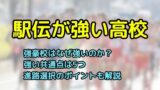


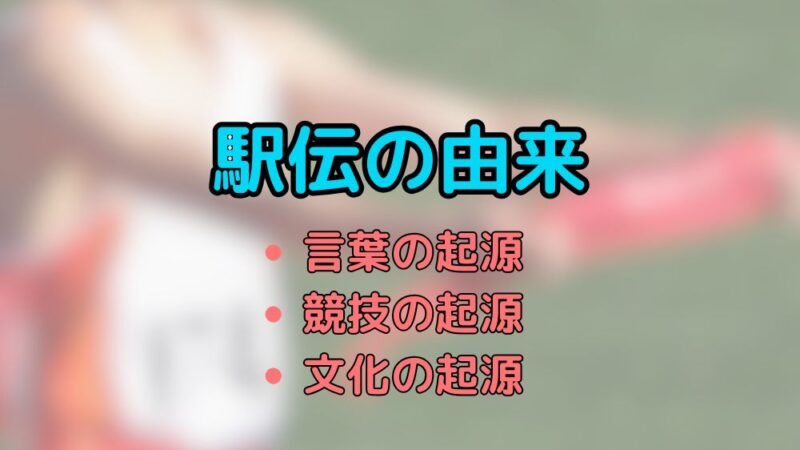
コメント