たすきの受け渡しは駅伝で順位を左右する重要なポイントです。
たすきの渡し方のポイントを押さえると、安定感のあるスムーズなタスキリレーができます。
本記事では、小学生から社会人まで全世代のランナー向けに、たすき渡しの基本ルールから渡し方のコツ、実践チェックリストまでを詳しく解説。
練習の段階から意識すべきポイントを押さえ、安心・安全にたすきをつなぐ方法を学びましょう。
たすきの渡し方が駅伝で重要な理由
駅伝で「たすきをつなぐ瞬間」は、ただの走者交代ではなく、チームの想いを受け継ぐ特別な場面です。
私(マー)も現役時代のたすき渡しの瞬間を今でも覚えています。
しかし、どんなに力強く走ってきても、たすきの受け渡しで手間取ってしまえば貴重な数秒を失い順位に大きな影響が出てしまいます。
さらに、慌てたたすき渡しは接触事故や失格につながるリスクもあり、選手自身の安全にも関わります。
そのため、駅伝に参加するすべてのランナーが「より良いたすきの渡し方」を知り、練習しておくことが欠かせません。
私自身、小学生に駅伝練習を指導して何度も優勝を勝ち取った経験がありますが、走る指導と同等にタスキの受け渡し指導も重要です。
まずはたすき渡しの基本ルールを確認しましょう。
駅伝のたすき渡しに関するルール・規定
駅伝で使用されるたすきには、大会ごとに基本的なルールや規定があります。
これらを守ることは、公平性を保つだけでなく、スムーズで安全な受け渡しにつながります。
具体的なルールを整理してみましょう。
タスキの規格
- 長さ:おおよそ1,600〜1,800mm
- 幅:約6cm
- 素材:布製で、肩から斜めに掛けられる仕様
大会によって多少の差はありますが、いずれも「走りながら掛けやすいこと」「落下しにくいこと」が重視されています。
中継所での受け渡し区間
- たすきを渡せるのは、定められた受け渡しゾーン内のみ
- ゾーン外での受け渡しは失格やペナルティの対象になる場合あり
- 中継所は混雑するため、あらかじめ自分たちの立ち位置や進入ルートを確認しておくこと
NG行為
- タスキの投げ渡しは禁止:安全性の観点から、手渡し以外は不可
- たすきを地面に落とす:拾い直しに時間がかかり、接触事故のリスクあり
- 区間外での受け渡し:失格の可能性あり
駅伝はスピード勝負であると同時に、規則を守ってこそ成立する競技です。ルールをしっかり理解して、「たすきのより良い渡し方」に集中しましょう。
よくある「まずいたすきの渡し方」
たすきの受け渡しは一瞬の動作ですが、ちょっとした油断や準備不足が失敗につながります。
ここでは、実際にありがちな「まずいたすきの渡し方」とそのリスクを紹介します。
片手で適当に差し出す
前走者がたすきを片手で軽く差し出すと、受ける側がたすきを受け取りづらく、落とす可能性があります。
結果的にたすきを拾い直す時間がかかり、大きなロスにつながります。
動線が合わずにぶつかる
前走者と次走者の走る位置や体の向きがバラバラだと、接触して体勢を崩す危険があります。特に混雑する駅伝の中継所では転倒事故にもなりかねません。
たすきを丸めたりねじったまま渡す
たすきが丸まっていたり、ねじれたままだと、次走者が素早く肩に掛けにくくなります。特に駅伝初心者や小学生ランナーは時間がかかりやすく、焦りを生む原因になります。
スピードが合っていない
前走者が急減速したり、逆に次走者の動き出しが遅れると、たすき受け渡しのタイミングがズレます。立ち止まったり、余計な並走を強いられたりして、体力やタイムを消耗することになります。
「まずい渡し方」の多くは、準備不足や動線の不一致から起こります。
次章では、これらのミスを防ぎ、スムーズにタスキをつなぐための「より良いたすきの渡し方」のポイントについて詳しく解説していきます。
より良いたすきの渡し方のポイント
たすきをタイムロスなくスムーズに受け渡すには、基本ルールを守るだけでなく、実践的なテクニックが欠かせません。
ここでは、誰でも実践できる「より良いたすきの渡し方」のポイントを紹介します。
①体の向き・進入ルートを合わせる
次走者は前走者の進入ルートに沿って待機するのが理想です。
前走者はラストスパートをかけたり、疲労困憊になっていたりと、周囲が見えていない場合がほとんどです。
そのため、次走者が前走者の進入ルートに合わせましょう。
接触や転倒のリスクを防ぎ、自然な流れでタスキの受け渡しができます。
②たすきの持ち方
前走者はたすきを両手でピンと張った状態にして差し出しましょう。
たすきを丸めるような形にすると次走者が通すまでに手惑います。
次走者が走りながら肩に通しやすいようたすきを張った状態に整えておきます。
ただ、たすきを外した後、丸めて走るランナーも中にはいます。
私もたすきを手にグルグルと巻いてラストスパートしていました。
その方が腕振りが力強くなり、加速できるからです。
小学生にもそのように教えていました。
最終的に、たすきを渡す直前でしっかりと張った状態にできればOKです。
③たすきを受け取る手は右手?左手?
たすきを受け取る手にルールがあるわけではありませんが、右手で受け取るランナーが多いです。
前後の区間でどちらの手で受け取るかを確認しておくと良いです。
次走者が右手で受け取る場合、前走者は右側を走り抜けていく意識でたすきを渡します。次走者が左手で受け取る場合は左側に走り抜けていく意識です。
この意識があれば味方同士の接触は防げます。
④たすきを渡すタイミングと走りながらの動き
受け渡し区間では、前走者と次走者が数メートルほど並走する形がベストです。
前走者はスピードを急に落とさず、自然な流れでたすきを渡します。
次走者は前走者のスピードに合わせて助走しながらスタートし、タイミングを合わせましょう。
次走者はたすきを受け取ったらスピードアップし、まずはレースの流れに乗りましょう。数十メートルほどで走りが安定したら、タスキの向きや形を確認して落ち着いて掛けましょう。
⑤たすき渡しの練習
たすきの受け渡しは、実際にやらないと感覚がつかめません。
練習あるのみです。
- チームで事前にたすきの受け渡しをシミュレーション
- 実際のスピードに近い状態で試す
- 右手・左手の使い方や並走距離を確認する
こうした練習を重ねておけば、本番でも慌てずに確実にたすきをつなぐことができます。
世代・レベル別のたすき渡しのポイント
たすきの渡し方の基本は共通していますが、世代や競技レベルによって意識すべきポイントは異なります。
ここでは、小学生から社会人・実業団まで、それぞれの状況に応じた注意点をまとめます。
小学生・初心者ランナー
- 安全最優先:走りながらの受け渡しが難しければ、立ち止まって確実に渡してOK。
- 声かけを重視:「いくよ!」「お願い!」と声をかけるだけでスムーズさが格段にアップ。
- たすきを掛けるサポート:受け取る側が自分で肩に掛けられない場合は、前走者がしっかり通す
中高生・市民ランナー
- スピードと安全の両立がポイント
- 中継所での走路位置や立ち位置を事前に確認しておく
- 部活や練習会などで、実際のペースを想定したたすき受け渡し練習を繰り返しておく
大学・実業団レベル
- 一瞬のロスが勝敗に直結するため、並走の距離や渡す瞬間の動きまで徹底的に練習
- 右手・左手の使い分けはもちろん、体の角度や声かけのタイミングも統一
- 本番では、選手間の信頼関係がスムーズな受け渡しに
たすきの渡し方以外で気をつけたいポイント
たすきの受け渡しをスムーズに行うためには、渡す瞬間だけでなく、普段の扱いや掛け方にも注意が必要です。
ここでは、渡し方以外で気をつけたいポイントを整理します。
①たすきの結び方
たすきは大会ごとに用意されたり、自チームで用意したりしますが、サイズ調整が必要な場合もあります。
走っている途中でほどけないよう、しっかり結んでおくことが大切です。
結び目が大きすぎると肩に掛けにくくなるため、コンパクトに整える工夫をしましょう。
②たすきの掛け方
斜め掛けが基本ですが、体格に合っていないと走っている最中にずれてしまいます。
体にフィットする位置に調整しておきましょう。
また、たすきが胸元を圧迫すると呼吸が苦しくなることがあります。走りやすさを優先した掛け方が重要です。
③中継所での注意点と荷物管理
次走者は中継所で余裕を持って準備しておくことが大切です。
前走者が中継所に来ていることに次走者が気づかず、たすきの受け渡しが遅れることがまれにあります。
招集(点呼)の時刻はもちろんですが、前走者が到着する時刻を予想し、ウォーミングアップなどの準備をしましょう。
また、荷物やジャージは走路を妨げない位置に置き、他チームの選手の動線を塞がないように気をつけましょう。
荷物置き場は、前走者が走り終えて休む場にもなります。できる限り日陰の場所にできると良いです。
④混雑時の周囲への配慮
多くのチームが参加する大会では、中継所が混雑しやすくなります。
たとえば、年末の全国高校駅伝では都道府県の数(あるいはそれ以上の数)が参加するため中継所は混雑します。
1区のたすき渡しはまさに激戦。熾烈なポジション取りを見たことがある人も多いでしょう。
以下に点に気をつけましょう。
- 周囲の選手に接触しないように、距離を保つ
- 大きな声で前走者を呼ぶ
- 無理に前に出ようとせず、流れに合わせる
これらを徹底することで、自分のチームだけでなく他チームの安全も守れます。
たすき渡し前後に確認すべきこと【 実践チェックリスト】
駅伝のたすき渡しは、レースの流れを左右する重要な場面です。
練習の中で流れを確認し、当日に慌てないようにするためにはチェックリスト化が効果的です。
以下のポイントを事前に意識しておきましょう。
たすき渡し前のチェックポイント
- たすきの状態(レース前):たすきが掛けやすい形になっているか
- 走行位置の確認:最後の100mでどのライン(進入ルート)を通るかを決め、次走者に分かりやすく伝える
- タイミング:受け渡し直前にどの程度のスピードで渡すか練習で共有する
- 掛け声の準備:チームで決めた声かけ(名前・合図)を使えるか確認する
たすき渡し時のチェックポイント
- たすきの渡し方:たすきをピンと張る
- 体の向き:体のどちら側から渡すかを統一する
- 目線の合わせ方:次走者の腰か胸を見るとスムーズに動きを合わせられる
たすき渡し後のチェックポイント
- 送り出しの声かけ:次走者の背中を押すように「行け!」と送り出す習慣
- 進路の確保:渡した後はすぐに走路外へ抜け、他チームの妨害にならないよう注意
- たすきの掛け方:たすきを受け取って、掛けるまでを練習
- 気持ちの切り替え:渡し終えたら速やかに次の役割(応援・体調回復)に
このチェックリストを繰り返し確認したり練習したりすることで、たすきの受け渡しがチーム全体で安定し、レースでのロスを最小限に抑えることができます。
まとめ
たすきの受け渡しは、駅伝における「勝敗を左右する重要な瞬間」であり、「チームの絆を象徴」する場面です。
数秒のロスや受け渡しミスは順位に直結するため、ただ走るだけでなく、たすきを確実に渡すスキルも同じくらい大切です。
本記事で紹介したポイントを意識し、たすきの持ち方・渡し方・体の向き・並走距離など、受け渡しの精度を向上させていきましょう。
たすき渡しの一つひとつのポイントが、チームの勝利と笑顔につながります。
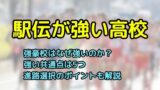


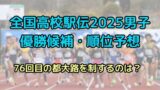

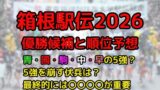
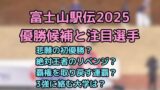
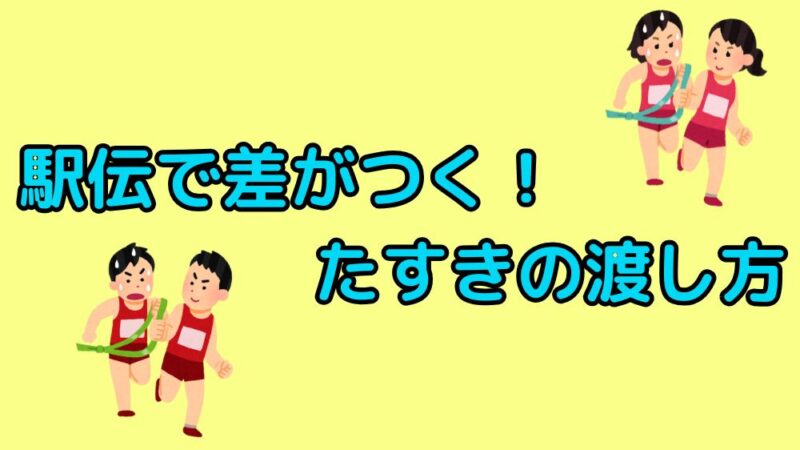
コメント